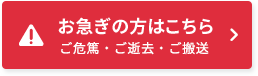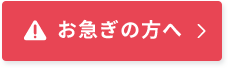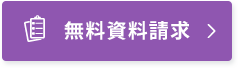七日七日とは?家族葬で知っておきたい仏事の基本
葬儀を行う中で、多くの方が耳にする「七日七日(なぬかなぬか)」という言葉。しかし、その意味や具体的な行事内容について詳しくご存じの方は少ないかもしれません。今回は、尾張旭市の家族葬専用式場「家族葬のソウネ」から、七日七日の重要性とその流れを分かりやすくお伝えします。この記事は、瀬戸市や尾張旭市でご葬儀をお考えの方にとっても役立つ内容です。
七日七日とは
「七日七日」とは、仏教における伝統的な供養の習慣で、故人が亡くなった日を含めて7日ごとに供養を行うものです。この七日ごとの法要は「初七日(しょなぬか)」から始まり、七回目の「七七日(しちしちにち)」、すなわち四十九日まで続きます。四十九日は、特に重要な節目とされ、故人の魂が現世と来世を区切る「中陰」としての役割を果たします。
各七日法要の意味と目的
各七日の供養には、それぞれ異なる意味が込められています。
- 初七日:葬儀の際に行われることが多く、亡くなった直後に遺族や親しい人々が集まって供養します。この日から故人が冥界で旅を始めるとされ、遺族は故人が無事に旅を続けられるよう祈ります。
- 二七日(にしちにち)・三七日(さんしちにち):故人が冥界で試される期間とされており、遺族は故人が善行を積んでいたことを祈り、冥界での試練を乗り越えられるよう供養します。
- 四七日・五七日・六七日:故人が少しずつ来世に近づく過程を象徴しています。各法要では、遺族が故人のために祈りを捧げ、その冥福を願います。
- 七七日(四十九日):この日が最終的な節目となり、故人の霊が無事にあの世に行けるよう祈ります。多くの場合、四十九日をもって忌明けとし、この後、日常生活に戻ることができます。

家族葬での七日七日法要
家族葬や一日葬が一般的となっている現在でも、七日七日の法要は行うことが可能です。特に尾張旭市や瀬戸市では家族の絆を大切にする風習があり、故人を偲ぶ時間を持つことで、残された人々が心を落ち着かせるきっかけになります。
「家族葬のソウネ」では、家族だけの温かい雰囲気の中で、七日七日の法要をサポートしています。直葬などのシンプルな葬儀の場合も、後日改めて法要を行うことができ、遺族の心の区切りをつける大切な時間を提供します。
七日七日の必要性と心構え
高齢者の方々にとって、七日七日は故人と向き合い、別れを受け入れるための大切な期間です。現代では、一日葬や直葬が増える中、法要を省略するケースも見受けられますが、遺族が集まり祈ることで心が癒され、思い出を共有する貴重な場になります。
葬儀や法要についての詳細は、「家族葬のソウネ」までお問い合わせください。尾張旭市や瀬戸市を中心に、温かく安心できる家族葬を提供しています。ぜひ一度、ご相談いただければと思います。
まとめ
七日七日という仏事は、故人の魂を送り出し、残された家族の心の整理をするための大切な行事です。尾張旭市や瀬戸市の方々にとって、家族葬や一日葬の中でどのように七日七日を取り入れるかを考えることは、より深い供養の意味を見出すことにつながるでしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
愛知県尾張旭市・瀬戸市・長久手市の葬儀から供養をトータルサポート
地域密着で24時間365日いつでも対応
石高石材販売グループ
家族葬のソウネ ☎0120-144-940
尾張旭市井田町3-205
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー